日経平均株価の分析
証券税制の改正やネット取引の手数料引き下げなどによって、個人でも手軽に株取引を行う事が出来るようになりました。書店には、個人投資家をターゲットにした株式投資に関する本が溢れています。そのなかでは多くの専門家と言われる人達が、さまざまな手法を用いて将来値上がりするであろう銘柄を推奨しています。また証券会社においても株価の予測には大きな比重が置かれ、日々多くのアナリスト達がレポートを書いています。
しかし、株価の予測をするということは本当に可能なのでしょうか?
効率的市場仮説によれば、株価はランダムウォークをするとされており、テクニカル分析やファンダメンタル分析は株価の予測には全く役に立たないと言われています。しかし一方では、行動経済学者などの手によって、効率的市場仮説に対する反例(アノマリー)が数多く報告されています。
もちろんこれは、どちらが正しいという問題ではなく、株式市場はある程度は効率的であり、また同時に非効率的であると考えられます。では、その程度はどのくらいなのでしょうか?アナリストのレポートを見て飛びつけば間に合うのか?ハウツー本の手法を真似すれば儲けられるのか?一般の個人投資家にとっては、この辺りが一番知りたいところです。
そこで、日本の株式市場はどの程度効率的なのかを検証するため、日経平均株価の分析を行いました。用いたデータは1991年1月から2004年6月までの13年6ヶ月分です。まずはこの期間の日足チャートを示します。
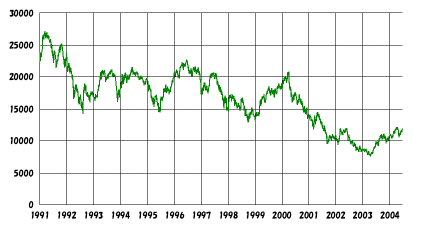
1991年のはじめ、バブル崩壊後ではありますが、今から考えれば24,000円は信じられないような値段です。その後10年程15,000円から20,000のレンジで動いた後、ITバブルが崩壊し、7,600円まで下がります。そして1年かけて回復し、現在は12,000円前後で取引が行われています。いわゆる失われた10年という期間のデータです。
まずは、基本的な統計量を示します。
| 日数 |
3321 |
|
| 平均 |
16648.94 |
|
| 分散 |
19174212 |
|
| 標準偏差 |
4378.84 |
|
| 最高値 |
1991/3/18 |
27146.91 |
| 最安値 |
2003/4/28 |
7607.88 |
13年6ヶ月の間に株式市場が開いていた日数は3321日、株価の単純平均は16648円でした。高値は1991年の27,000円、安値は2003年の7,600円です。
このデータを用いて、日経平均株価がランダムウォークしているかどうかを検証します。まずは、当日の終値から前日の終値を引いて、一日の変動幅を計算します。株価が上がった日はプラスの値、下がった日はマイナスの値となります。3321日のうち、値上がりした日が1629日(49.05%)、値下がりした日が1692日(50.95%)でした。2%ほどの差がありますが、有意な差ではないように思います。
次に株価の水準に関係なく比較を行うため、変動率を算出します。変動率の定義は
変動率[%] = (当日の終値 - 前日の終値) / 前日の終値 * 100
です。変動幅と変動率についての、平均、分散、標準偏差の値を示します。
| 変動幅 |
変動率 |
| 平均 |
-3.68 |
平均 |
-0.010 |
| 分散 |
58385 |
分散 |
2.223 |
| 標準偏差 |
241.63 |
標準偏差 |
1.491 |
次に、変動率の傾向を確認するために棒グラフを示します。横軸が日にち、縦軸が変動率になっています。ところどころ分散が大きくなっているような時期があるようにも見えますが、規則性を見出せるほどではないようです。
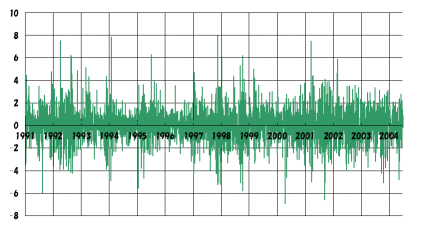
次の表は、変動幅、変動率が大きかった日を抜き出したものです。期間中に1,000円を超える暴騰が6回、1,000円以上の暴落が3回起こっています。また5%以上の暴騰、暴落はそれぞれ10回以上ありました。
暴騰と暴落を比較すると、暴騰の方がやや変動率が大きくなっています。7%以上の暴落は一回もありませんが、暴騰は4回あります。多くの人は感覚的に、暴騰よりも暴落の方が大きいと感じていると思われます。そのため、この結果はやや意外な感じを受けるのではないでしょうか?おそらく原因は、暴落については資金が減った事が強く印象に残るのに対し、暴騰してもあまり印象に残らないためではないかと思います。
暴騰の方がやや変動が大きいという結果が出ましたが、これについても有意な差ではないと考えられます。また、ここにあがっている日は、歴史的な暴落や暴騰の日ですが、統計的に見ると決して特別なことではなく、むしろ通常のランダムウォークの結果であると言えます。
| 上昇幅ランキング |
|
上昇率ランキング |
| 順位 |
日付 |
上昇幅 |
上昇率 |
|
順位 |
日付 |
上昇幅 |
上昇率 |
| 1位 |
1994/1/31 |
1,471.24 |
7.84% |
|
1位 |
1997/11/17 |
1,200.80 |
7.96% |
| 2位 |
1992/4/10 |
1,252.51 |
7.55% |
|
2位 |
1994/1/31 |
1,471.24 |
7.84% |
| 3位 |
1997/11/17 |
1,200.80 |
7.96% |
|
3位 |
1992/4/10 |
1,252.51 |
7.55% |
| 4位 |
1991/12/13 |
1,042.33 |
4.80% |
|
4位 |
2001/3/21 |
912.97 |
7.49% |
| 5位 |
1992/8/27 |
1,013.35 |
6.13% |
|
5位 |
1995/7/7 |
956.19 |
6.27% |
| 6位 |
1991/1/17 |
1,004.11 |
4.47% |
|
6位 |
1992/8/21 |
949.12 |
6.22% |
| 7位 |
1995/7/7 |
956.19 |
6.27% |
|
7位 |
1998/10/7 |
803.97 |
6.17% |
| 8位 |
1992/8/21 |
949.12 |
6.22% |
|
8位 |
1992/8/27 |
1,013.35 |
6.13% |
| 9位 |
1998/1/16 |
924.47 |
6.11% |
|
9位 |
1998/1/16 |
924.47 |
6.11% |
| 10位 |
2001/3/21 |
912.97 |
7.49% |
|
10位 |
2002/3/4 |
638.22 |
5.90% |
| |
|
|
| 下落幅ランキング |
|
下落率ランキング |
| 順位 |
日付 |
下落幅 |
下落率 |
|
順位 |
日付 |
下落幅 |
下落率 |
| 1位 |
2000/4/17 |
-1,426.04 |
-6.98% |
|
1位 |
2000/4/17 |
-1,426.04 |
-6.98% |
| 2位 |
1991/8/19 |
-1,357.61 |
-5.95% |
|
2位 |
2001/9/12 |
-682.85 |
-6.63% |
| 3位 |
1995/1/23 |
-1,054.73 |
-5.60% |
|
3位 |
1991/8/19 |
-1,357.61 |
-5.95% |
| 4位 |
1994/1/24 |
-954.19 |
-4.94% |
|
4位 |
1998/10/8 |
-799.55 |
-5.78% |
| 5位 |
1997/11/19 |
-884.11 |
-5.29% |
|
5位 |
1995/1/23 |
-1,054.73 |
-5.60% |
| 6位 |
1997/11/25 |
-854.05 |
-5.11% |
|
6位 |
1997/11/19 |
-884.11 |
-5.29% |
| 7位 |
1992/1/8 |
-851.39 |
-3.61% |
|
7位 |
1997/12/19 |
-846.75 |
-5.24% |
| 8位 |
1997/12/19 |
-846.75 |
-5.24% |
|
8位 |
1997/11/25 |
-854.05 |
-5.11% |
| 9位 |
1991/1/8 |
-838.73 |
-3.53% |
|
9位 |
1998/9/11 |
-749.05 |
-5.11% |
| 10位 |
2000/5/11 |
-819.01 |
-4.63% |
|
10位 |
2003/10/23 |
-554.46 |
-5.09% |
次に日経平均株価のヒストグラムを示します。6,000円から28,000円までを250円刻みで区切り、終値がその範囲内にあった日数をカウントしました。21,000円、18,000円、17,000円の周辺にそれぞれ山があるように見えます。これは1992年から2001年の間、この辺りの価格帯で推移していたことが原因でしょう。1993年、1994年、1997年、2000年と20,000円まで騰がっては下がるというのを繰り返しています。いわゆる跳ね返されるという現象です。また10,000円から11,000円のところにもピークがあります。これは2001年の終わりにここで一旦下げ止まった事、2003年に一旦調整が入った事が原因です。
こうして見るとどうやら、10,000円、20,000円といったキリのよい数字が意識されている可能性があります。しかし、この現象が確かにあるとしても、それを利用して実際に平均以上の収益があげられるかはまた別の問題です。これについては詳細な検証の価値があると思います。ただし、日経平均株価よりもTOPIXの値を重視する人の割合など、定量化の難しい要素も多いので、正確な検証は困難だと思われます。
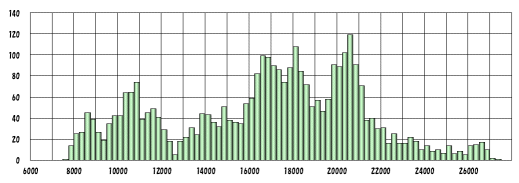
次に一日の変動率についてのヒストグラムを示します。+10%から-10%を0.2%刻みで区切り、一日の変動率がその範囲にある日数をカウントしました。横軸が変動率、縦軸が度数になっています。0付近を中心にした正規分布であると見て問題ないようです。5%を超えるような暴騰や暴落も、このグラフからすると極めて自然な現象のように感じられます。
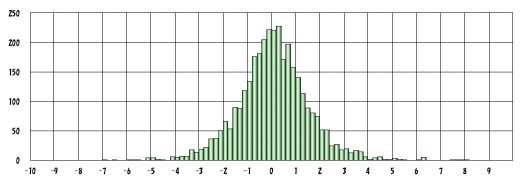
次に変動の連続性について検証します。感覚的には株価はある周期にそって変動しています。つまり上げ相場、下げ相場の時期というのが交互にやってきます。もしそうであるなら、日足レベルで見ても前日の値動きと当日の値動きの間に何らかの相関関係があることが期待されます。ここでは、その相関を見るため、横軸を前日の変動率、縦軸を当日の変動率とした散布図を示します。予想では、連続する2日間の変動率の間には弱い正の相関があると考えていたのですが、グラフからはそのような関係は全く見出せません。5%以上暴騰した次の日も、5%以上暴落した次の日も、同じような値動きとなっています。つまり、暴騰しているから慌てて飛びつくとか、暴落した日に処分売りするなどの行為は、統計的にはあまり意味のない行動ということになります。ちなみに相関係数は-0.0274となりました。
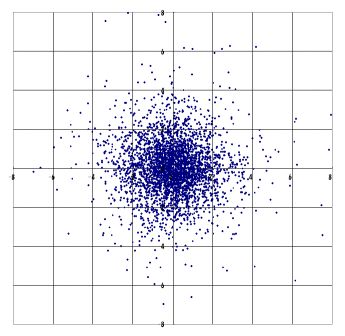
最近のJASDAQ市場を見ると、ランダムウォークでは説明出来ないような連続上昇を繰り返しているように思います。そこで日経平均株価でもそのような現象があったのかどうかを検証しました。下の表は連続して値上がりした日数、値下がりした日数をカウントしたものです。理論値は期間中に値上がりした日、値下がりした日の割合をもとに計算しました。
この表を見る限り、有意な特徴はないように思います。強いて言えば、2日間上昇した場合には、3日目に反落することは少なく、3連騰、4連騰、5連騰になることが多い、となりますが、おそらく誤差の範囲でのバラツキです。この傾向が今後も継続し、これを利用して平均以上に儲けることができるかは甚だ疑問です。
| 連続上昇 |
回数 |
割合[%] |
理論値[%] |
連続下落 |
回数 |
割合[%] |
理論値[%] |
| 1 |
447 |
51.56 |
49.08 |
1 |
453 |
52.31 |
50.92 |
| 2 |
198 |
22.84 |
24.09 |
2 |
216 |
24.94 |
25.93 |
| 3 |
117 |
13.49 |
11.82 |
3 |
106 |
12.24 |
13.20 |
| 4 |
58 |
6.69 |
5.80 |
4 |
52 |
6.00 |
6.72 |
| 5 |
31 |
3.58 |
2.85 |
5 |
25 |
2.89 |
3.42 |
| 6 |
7 |
0.81 |
1.40 |
6 |
8 |
0.92 |
1.74 |
| 7 |
5 |
0.58 |
0.69 |
7 |
3 |
0.35 |
0.89 |
| 8 |
2 |
0.23 |
0.34 |
8 |
3 |
0.35 |
0.45 |
| 9 |
2 |
0.23 |
0.17 |
9 |
0 |
0.00 |
0.23 |
| 10 |
0 |
0.00 |
0.08 |
10 |
0 |
0.00 |
0.12 |
ここでは、1991年1月から2004年6月までの13年6ヶ月分の日経平均株価の日足データを使って、株価がランダムウォークしているのかどうかを検証しました。その結果、株価の推移について有意な偏りは見られず、ほぼランダムウォークであることが確認出来ました。つまり少なくとも日経平均株価については、個人投資家レベルで普通にETFなどを用いて平均以上の利益をあげることは困難であると言えます。統計を取った訳ではないので断言は出来ませんが、投資関係の月間誌などに載っている専門家と言われる人たちの予想も、的中率は5割程度であると考えられます。
少なくとも日本の株式市場は、翌日の平均株価を予測出来ない程度には効率的であると結論します。